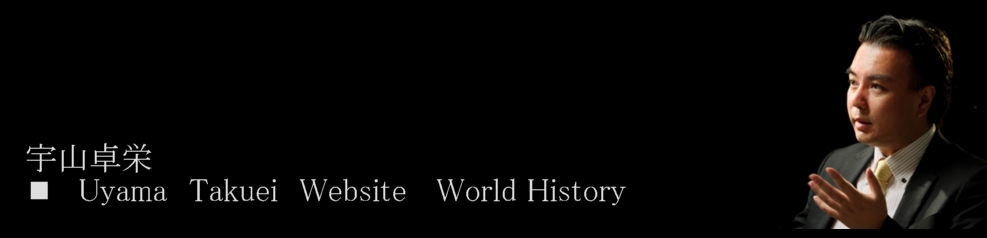 .
. 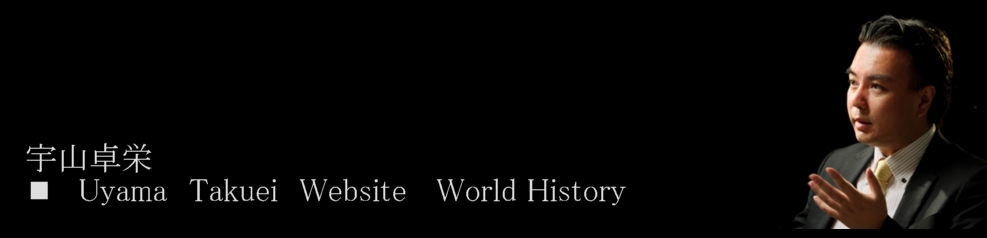 .
.
■ Column コラム
2015年02月【歴史・教育】「バロック」をどう説明するか
・バロックという概念
教科書や概説書では17〜18世紀にバロックが隆盛し、その後、古典主義が定着するという順序で説明がなされます。激しい動きのあるバロック様式に対する反動として、理性的でスタティック(静的)な古典主義が現れた、というのが一般的な説明です。バロック絵画やバロック音楽というものはあるのですがバロック文学というものは基本的にありません。
バロックの一般的な定義として、「絶対王政とカトリックの威信を高める使命をもち、激しく力強い動感、劇的な感情表現、豪華絢爛な装飾性を特徴とする」と説明されます。バロック絵画の巨匠ルーベンスの作品はなるほど、ダイナミックで動きがあり、バロック様式の定義とよく符号します。しかし、同じバロック絵画とされるベラスケスの作品には「激しい動き」はどこにもなく、静寂で冷厳な印象が強く、むしろ古典主義の定義に近いと言えます。同時代のプッサンやクロード・ロランの絵画は古典主義とされ、バロックとはされません。音楽に関して、バロック音楽と古典主義の音楽の違いはどこにあるのでしょうか。
バロックとは表現の性質・特徴を指す「様式上の定義概念」なのか、絶対王政やカトリックの威信を示すためのモチーフ(題材)を指す「主題上の定義概念」なのか、或いは時代区分を指すものなのか。これらのことを突き詰めていくと、大きな混乱が生ずるでしょうから、教科書や一般書ではバロックというものがどの様なものかを明確に述べず、ボカして、曖昧にしています。学習者の困惑は勿論のこと、教師までもが問われれば答えに窮してしまいます。
バロックとはポルトガル語で「歪んだ真珠」という意味で、これが何故、芸術の世界で使われるようになったのか、詳しいことはわかっていません。当初は技術の拙劣を嘲笑して、「ガタガタ」で下手、というくらいの意味で使っていたらしく、このことからもわかるように、17〜18世紀の当時の人々が自分たち自身をバロックと呼んでいたわけではありません。後世の18〜19世紀の人々が前時代の芸術を嘲笑するときにバロックと呼んだのです。特に音楽の分野でハイドン、モーツァルトなどの洗練された和声音楽が流行したとき、前時代のバッハの対位法に基づいたバロック音楽が、「ガタガタ」したいびつなものに聞こえて、「バロック」と嘲笑されたといいます。
1855年になって、スイスの美術史家ヤーコプ・ブルクハルトがバロックという語をルネサンス後の17〜18世紀の芸術を総称するために学術的に使い、当初の侮蔑的な意味が消えていきました。20世紀には同じくスイスの美術史家ハインリヒ・ヴェルフリンが著書『美術史の基礎概念』でバロックをルネサンス芸術へのアンチテーゼとして定義し、今日の教科書などで使われる一般類型のルーツとなります。
・バロック絵画の諸作品
バロックの一般的な定義説明の「絶対王政とカトリックの威信を高める使命」という部分は「主題上の定義概念」を示し、「激しく力強い動感、劇的な感情表現、豪華絢爛な装飾性を特徴とする」という部分は「様式上の定義概念」を示しています。ルーベンスの代表作『マリー・ド・メディシスの生涯』はそのどちらの定義概念も兼ね備えており、バロック絵画の典型といえます。ルネサンス末期からバロック初期に活躍したエル・グレコの宗教画もまた、主題・様式の両定義概念を兼ね備えています。
ルーベンスの弟子ヴァン・ダイクは師と同じフランドル(現ベルギー)の出身ですが、イギリスに渡り、チャールズ1世の宮廷画家となりました。肖像画を得意としたヴァン・ダイクは当代随一のデッサン家で、古典主義的な明晰で強靭な描写力で人気を博しました。ヴァン・ダイクは後の時代のイギリス古典主義美術に絶大な影響を与え、古典主義の元祖とされる一方で、バロックに分類されるのは彼がルーベンスの弟子であったこと、絶対王政期のチャールズ1世に仕え、王や王一家の肖像を多く描いたことなど、つまり「主題上の定義概念」によるものと考えられます。
レンブラントは『夜警』で市民たちの自治と治安維持活動の様子を描きました。レンブラントの生きた17世紀のオランダはスペインからの独立を果たし、共和国となりました。『夜警』は共和国オランダにおける市民の自主独立の気概を示すものでバロックの一般的定義とされる「絶対主義国家やカトリックの威信」を示すものは見られません。レンブラントの作品のモチーフ(題材)にはバロック的な要素はありませんが、レンブラントの作品表現のスタイル(様式)にバロック的な特徴が見られます。強烈な光と影の強いコントラストによって描刻された人物の劇的なダイナミズム、強い陰影が写し出す彫塑的形態の迫真はバロック的特徴の典型の一つと言えます。
ベラスケスはスペインの画家で、スペイン絶対主義を築いたフェリペ2世の孫フェリペ4世の宮廷画家として、『ラス・メニーナス』などの国王一家の肖像画を数多く描きました。ベラスケスはイタリア訪問の折、時の教皇インノケンティウス10世の肖像画を描きました。ベラスケスの『十字架上のキリスト』はキリスト磔刑図の最高峰とされます。この様にベラスケスの作品のモチーフは「絶対王政やカトリック教会の威信を高める使命を持つ」というバロックの「主題上の定義概念」によく当てはまっています。その一方で、ベラスケスの作品はバロック的なダイナミズム、激しい動きはなく、冷厳な統制と静かな調和が特徴です。従って、ベラスケスをバロックとして扱うとき、作品のモチーフ(題材)にバロック的要素が認められると判断できます。
レンブラントと同じオランダの17世紀の画家フェルメールは穏やかな市民の生活空間と人物を題材とした作品を残しました。フェルメールの作品にはレンブラントのような光と影のコントラストの効果が認められますが、その表現スタイル(様式)は劇的と言い難く、バロック的ダイナミズムを持つ作品として捉えることはできません。また、フェルメールの作品の題材は絶対主義や神を標榜するものでもありません。しかし、フェルメールが一般的にバロックと分類されるのはフェルメールが単にバロック時代に生きたということだけの理由です。フェルメールの作品にはスタイル(様式)においても、題材においてもバロック的なものは何もありません。
このようにバロックという定義に嵌まらないフェルメールの存在は教科書では意図的に除外されてしまっています。教科書ではバロックという概念を無理に中心に据えようとし、それにそぐわない都合の悪いものが作為的に消されているのです。教科書による、こうした作為的除外の例はフランスのプッサンやクロード、ル・ブランにも当てはまります。彼らは当時、隆盛を誇っていたルーベンス派に反発し、抑制の利いた均衡と調和を主張した古典主義者です。17世紀前半に活躍したニコラ・プッサンは代表作『アルカディアの牧人』などの歴史画、神話画を題材として、厳格な形態と構図による静的な安定を表現しました。プッサンと同時代のクロード・ロランは古典主義的な風景を多く描きました。
シャルル・ル・ブランはルイ14世の宮廷画家として活躍し、財務大臣コルベールの支援を受け、1648年、王立絵画・彫刻アカデミーを設立しました。コルベールとル・ブランはアカデミーを中世的なギルド(組合)に代わる、絶対王政の政府文化機関として組織し、思想統制と美術の中央集権化を図りました。当時フランスの美術界では、ルーベンス派(動的)とプッサン派(静的)が激しい派閥争いを展開していましたが、プッサン派に属するル・ブランはルーベンス派を制し、ルーベンス的なスタイルを退け、厳格な古典主義に基づいたアカデミーの理論を構築しました。
以後、アカデミーはプッサンの古典主義の理論を基盤とする古典主義の牙城として美術界を支配しますが、19世紀には写実主義や印象主義の反乱に見舞われます。写実主義や印象主義は古典主義を標榜するアカデミーへの反動として生まれたのです。故にプッサン的なアカデミーの存在を無くして、19世紀の絵画を語ることはできません。それにも関わらず、17世紀のプッサン、ル・ブランの存在は教科書では一切扱われず、教科書ではあくまでバロック絵画が17世紀の中心で、それ以外のものはまるで存在しなかったかのように説明されます。
前述のレンブラントたちをバロックと分類したときに、その基準となるものはレンブラントの場合は作品の描かれ方(性質)であり、ベラスケスやヴァン・ダイクの場合は作品のモチーフ(題材)です。フェルメール、プッサンやクロード、ル・ブランなどバロックという定義で捉え切れないものは曖昧にしてごまかすか、記述削除されています。この事例からも分かるように、バロックという概念は合成的な「つぎはぎ」に過ぎないのであり、当時の実態をリアルに捉えるような総括的概念とは到底言えるものではなく、その定義の基準は個別の芸術家それぞれにバラバラに適応され、統一的根拠がありません。本来ならば、バロックという曖昧な類型概念は美術史において、使われるべきではありません。
バロック絵画とされている作品は多種多様で、とても一括りにまとめられるものではないのですが、これを無理にまとめようとするために、錯誤が生じてしまいます。
・バロック音楽と古典主義音楽
しかし、一転して音楽史においては、バロックという概念は有効な類型基準になり得ます。バロックは美術史と違い、音楽史においては明確で一貫した定義付けが可能です。
五線譜に音符を記す近代記譜法はルネサンス時代末期の16世紀に定着し、17世紀〜18世紀のバロック時代の音楽はこの五線記譜法で書かれます。ルネサンス時代の音楽はグレゴリオ聖歌に代表されるようにモノフォニー(単旋律)の音楽でした。モノフォニーはただ一つの声部からなる音楽で単声部音楽とも言います。五線記譜法の確立により、音楽の構造は複雑で多彩になり、その技法は飛躍的に発展し、ポリフォニー(複旋律)音楽が隆盛します。ポリフォニーは多声音楽とも言い、複数の声部が異なる動きをしながら協和しあって進行していく音楽です。それぞれの声部が独立し、同程度の比重で絡み合い、主旋律と伴奏の区別はなく、それぞれが対位します。こうしたことから、ポリフォニー技法は「対位法(フーガ)」とも呼ばれ、バロック音楽の大きな特徴となります。
イタリアのアントニオ・ヴィヴァルディ、ドイツのヨハン・セバスティアン・バッハ、ゲオルグ・フリードリヒ・ヘンデル、フランスのフランソワ・クープランなどがこれに当たります。美術史におけるバロックの定義における曖昧さとは違い、バロック音楽とはポリフォニー技法(フーガ技法)で書かれたものであり、その楽曲の性質や特徴を明確に示すものと定義することができます。
ホモフォニー(和声)音楽は和声・和音を楽曲の展開の推進力とし、主旋律・伴奏の区分によって、1声部のみが主旋律となり、他の声部はそれを和声などで支える役割を持ちます。各声部の独立した水平の流れを特徴とするポリフォニーに対し、ホモフォニーは音の垂直的な結びつき、和声的な流れを特徴とします。18世紀に始まるハイドンやモーツァルトらの古典主義音楽と、それ以降のロマン主義音楽はホモフォニー技法をとります。ホモフォニー(和声)技法を中心とする古典主義音楽はバロック音楽のような対位旋律の激しい拮抗は見られず、和声調和的です。調和と均衡を重視する古典主義からバロック音楽を見れば、「歪んだ真珠(バロック)」と形容される不揃いさが目立つことになります。
バロック音楽はその楽曲の性質を示す様式上の定義であり、時代区分を指すものではありません。バッハが生きた18世紀の前半は既に古典主義音楽が本格的に始まっていた時代で、バッハのバロック音楽は当時、時代遅れなものでした。
バッハは晩年に息子のカール・フィリップ・エマニュエルが宮廷音楽家として仕えていたプロイセン王フリードリヒ2世を表敬訪問しました。フリードリヒ2世はフルートの名手で大変な音楽愛好家であったのですが、バッハの古いバロック音楽には全く興味を示さず、当時の流行りの古典主義音楽に傾倒していました。18世紀前半はバッハのバロック音楽と新しい古典主義音楽が併存をしていた時代でした。このことからも分かるように、バロック音楽と古典主義音楽は性質上の違いで区別されものであり、時代区分の類型ではないことは明らかです。